Contents
予防・対策・改善方法まとめ
新年度が始まり、新しい環境での生活にも少しずつ慣れてきた頃。
しかし、4月の緊張が解けた5月に、なぜか「体がだるい」「気分が晴れない」「やる気が出ない」といった不調を感じる人は少なくありません。
これが、一般的に「五月病」と呼ばれる心身の不調です。
五月病は、正式な病名ではありませんが、真面目な人や責任感が強い人ほど陥りやすいと言われています。今回は、そんな五月病について、その原因から具体的な対策、そしてもしなってしまった時の改善方法まで、詳しく解説していきます。
五月病とは?なぜ5月に起こるの?
五月病とは、新生活への期待や緊張が緩み、その反動で心身に不調が現れる状態を指します。
4月の頑張りの反動
- 4月は新しい環境に適応しようと、私たちは無意識のうちに緊張し、無理をして頑張ってしまいます。この状態が1ヶ月続くと、心も体も疲労のピークに達します。
ゴールデンウィークの落とし穴
- 緊張状態がGWで一気に解き放たれ、連休明けに「また頑張らなきゃいけない…」という現実とのギャップに直面します。このタイミングで、4月の疲れが一気に噴き出してしまうのです。
気候の変化
- 5月は気温や天候が不安定な時期です。この急な変化が、私たちの自律神経を乱し、心身のバランスを崩す一因となります。
もしかして五月病?チェックしたい症状リスト
「五月病かもしれない…」と感じたら、まずは自分の心と体の状態をチェックしてみましょう。五月病の症状は、精神的なものと身体的なものに分かれます。
【精神的な症状】
- やる気が出ない、無気力になる
- 朝起きるのが辛い
- 以前は楽しかったことに興味が持てない
- 集中力が続かない、仕事や勉強が手につかない
- 憂鬱な気分になる
- 理由もなく気分が沈む、イライラしやすい
- 不安感や焦燥感を感じる
- 人との交流を避ける
- 誰にも会いたくない、話したくない
- 新しい人間関係がわずらわしく感じる

【身体的な症状】
- だるさや疲労感
- 睡眠を十分にとっても、疲れが取れない
- 睡眠障害
- なかなか寝付けない、夜中に何度も目が覚める
- 食欲不振
- 食べたいと思えない、食事が美味しく感じられない
- その他
- 頭痛、めまい、動悸、胃の不快感、肩こり、発汗など

これらの症状が2週間以上続いている場合は、五月病の可能性があります。
五月病を乗り越える!【予防・対策・改善方法】
五月病は、事前の準備と日頃の心がけで予防・軽減することができます。
【予防】4月のうちにやっておくべきこと
- 「完璧主義」を手放す勇気を持つ
- 新しい環境では、最初から完璧にこなそうとせず、**「60%の力でOK」**と自分に言い聞かせましょう。完璧を目指す頑張りが、大きな反動となって自分を苦しめます。
- 意識的に休息を取る
- 忙しい中でも、週末はしっかり休む、夜は早く寝るなど、意識的に休息の時間を確保しましょう。
- 小さな楽しみを見つける
- 「この仕事を終えたら、美味しいコーヒーを飲もう」「今日は早く帰って好きなドラマを観よう」など、日々の生活の中に小さなご褒美を設定することで、モチベーションを保てます。
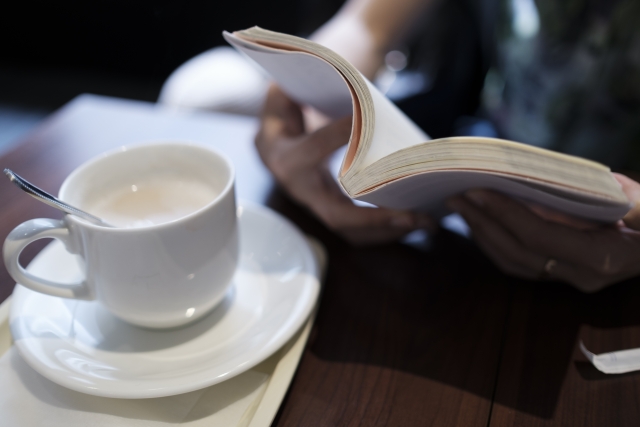
【対策】5月にできること
五月病の症状を感じ始めたら、自分を労るための対策を始めましょう。
【心のケア】
- 趣味の時間を持つ: 好きなことに没頭する時間は、心の栄養になります。映画を観る、音楽を聴く、読書をするなど、自分が本当に「楽しい」と感じることを優先しましょう。
- デジタルデトックス: SNSやスマホから少し離れる時間を作りましょう。他人と自分を比較する機会が減り、心穏やかに過ごすことができます。
- 誰かに話す: 信頼できる家族や友人に、今の気持ちを話してみましょう。話すだけでも心が軽くなり、客観的に自分を見つめ直すきっかけにもなります。

【体のケア】
- 睡眠の質を高める: 寝る1時間前はスマホやパソコンから離れ、ぬるめのお風呂にゆっくり浸かるなど、心身をリラックスさせてから眠りにつきましょう。
- バランスの取れた食事: 疲労回復を助けるビタミンB群や、自律神経を整えるカルシウムなどを意識して摂りましょう。
- 適度な運動: ウォーキングやストレッチなど、無理のない範囲で体を動かすと、血行が良くなり、気分転換にもなります。

【改善】症状が重いと感じたときの対処法
五月病は「心の風邪」のようなもの。無理に頑張ろうとせず、専門家の力を借りることも大切です。
- 無理に頑張らない: 辛いと感じたら、仕事や学業のペースを落とすことを検討しましょう。まずは休むことが最優先です。
- 専門家を頼る: 症状が長引く、または日常生活に支障が出ている場合は、一人で抱え込まずに心療内科や精神科を受診しましょう。早めに相談することで、症状の悪化を防げます。

周りの人が五月病かも…どう接する?
もし家族や友人が五月病の症状を抱えているようであれば、以下の点を意識して接してみてください。
- 否定せず話を聞く: 「甘えだ」「大したことない」といった言葉はかけずに、ただ黙って話を聞いてあげましょう。
- 無理に励まさない: 「頑張れ!」という言葉は、プレッシャーに感じてしまうことがあります。「ゆっくり休んでね」「いつでも話を聞くよ」といった、寄り添う言葉をかけてあげましょう。
- 専門家への相談を促す: 症状が重いと感じたら、「一度専門家に相談してみたら?」と優しく勧めてみましょう。

五月病は、誰にでも起こりうる、心の自然な反応です。
一人で抱え込まず、自分を労り、周りを頼ることで、必ず乗り越えることができます。



コメント